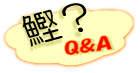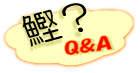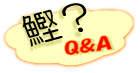 |
|
| ▼鰹ってどうやって捕るの? |
|
▼menu |
 |
|
|
|
| BACK |
|
|
|
|
| かつお一本釣り漁業の概要 |
| 高知海洋局資料 |
漁船規模 |
乗組員 |
漁期 |
| 遠洋・近海かつお漁業 |
50〜180トン |
15〜25人 |
2月中旬から11月 |
| 沿岸かつお漁業 |
5〜19トン |
4〜11人 |
盛漁期5〜6月、10月 |
| 沿岸かつお漁業の漁場5〜10トンの漁船の操業範囲は、ほとんどが土佐沖30マイル(約48キロメートル)以内
19トン型漁船の操業範囲は、薩南海域から遠州灘付近。 |
|
|
|
■鰹の漁は年2回
土佐沖では鰹漁が年に2シーズンあります。初鰹漁は大体3月末から7月上旬。その後、鰹は黒潮沿いに北上し三陸沖で夏を過ごしてから南下しはじめます。その鰹が再び土佐沖に姿を見せるのが大体9月末。それか11月いっぱいまで、脂たっぷりの戻り鰹漁が繰り広げられます。 |
 |
 |
■漁場は遥か沖の黒潮銀座
土佐の鰹漁は、昔もいまも一本釣が中心で、夜の10時〜11時に出港し、黒潮を目指して7〜8時間、150キロ〜200キロを航行する。漁場は黒潮の流れの中じゃなくて、ないだ海と黒潮本流の境目がポイント。プランクトンが大量に湧き、それをエサとするイワシ類が、さらに鰹などの大型回遊魚が集ります。 |
■ナブラを探して戦闘開始
漁場に着いたら、流れ物(流木や網・縄など)、ナブラ(魚群)の上を舞う鳥の群(マトリは鰹の居場所を漁師に教えてくれる)、サメ(主にジンベイザメ)、鯨などの影を追いかけて群れているのでとにかく海面の浮遊物、を探す。発見したら船をナブラのそばに付けて、まず生き餌のイワシを投入。鰹を足止めした後、勢い良く放水! 白く泡立つ海の中、鰹は興奮状態にさせて、そこでいよいよ竿を投げ入れる。針にかかったら一気に引き抜き、空中で針を外して船内に投げ入れる。まさに名人芸やね。 |
 |
 |
■一本一本心をこめて
「こんな面白い漁はない」と漁師が口をそろえる。一本釣りは豪快そのものやけど、釣り上げられる数は群れの1%ほど。ナブラを一網打尽にする巻き網漁とは、資源に対する優しさも、魚体の美しさや味も比較にないません。しかし40年間にわたり日本近海に回遊する鰹の大きさを調べた結果、1970年をさかいにとれる鰹のおおきさが小さくなってきている。これは、1970年代以降南方漁場の開発や、巻き網船の増加で、鰹の自然のサイクルを変化させたためである。
高齢産卵群が減ったために、これから生まれる鰹のグループが減って、若年産卵群に支えられるようになった、また遠洋の鰹の取りすぎで、鰹の絶対量が減ったために競争相手が少なくなって、日本の近海を回遊せず餌がとれるようになったため、日本近海にこなくなったのではないか。との報告もあります。 |
| カツオは早春から晩秋にかけて列島近海を回遊するため、前述したように時期によって漁場が移動する。カツオ一本釣り漁船は、そのカツオの群を追って移動しながら漁をするから、いちいち母港に戻るわけにはいかない。そこで、各漁船は漁の状況や前日セリ値を勘案しながら、そのつど、水揚げ港を選んで入港することになる。現在、主な水揚げ港は南から、鹿児島県枕崎港、同山川港、高知県土佐清水港、和歌山県那智勝浦港、静岡県御前崎港、同焼津港、同沼津港、千葉県勝浦港、同銚子港、茨城県那珂湊港、福島県中之作港、そして宮城県気仙沼港などである。 |
伝統的な漁法は、カツオの群の中に船を乗り入れて一尾一尾釣り上げる一本釣り[さお釣り]だが、これには主として二通りの方法がある。一つは、生き餌をまいて船の近くにカツオを集める方法で、もう一つは、疑似鉤[ぎじばり]と散水ポンプの組み合わせでカツオを呼び込む方法である。また、一本釣りといっても漁をする海域によって、沿岸一本釣り、近海一本釣り、遠洋一本釣りに分けられる。
一方、現在主流になっているのは、大型のカツオ・マグロ漁船による延縄や巻き網漁で、カツオが北上経路をたどって沿岸に近づく前に一網打尽にする。そのため、沿岸カツオ一本釣りの漁獲量は激減している。 |
|
|
|
| BACK |